WEBマーケはもう古い?最新デジタルマーケティングとは

2015年からよく耳にするようになった「デジタルマーケティング」という言葉。国内では”デジマ”という略称で呼ばれることもあるようです。このデジタルマーケティングは、これまで主流であったWEBマーケティングとはどう違うのか、これから先のマーケティング市場はどのように変化していくのか。
国内外のデジタルマーケティング事情からひも解いていきます。
Contents
Googleトレンドから見るデジタルマーケティングの注目度
2016年現在、Googleトレンドで国内の「デジタルマーケティング」「Webマーケティング」を検索した結果が以下です。
2005年から2009年の5年間では「WEBマーケティング」の検索数が圧倒的でしたが、2010年あたりから「デジタルマーケティング」の検索数が増え始め、遂に今年2016年には検索数が完全に一致(見方によっては少し上回って)います。このグラフを見る限り、2017年には完全に「デジタルマーケティング」の検索数が上にいくでしょう。
※2017/03/18追記:Googleトレンドのキャプチャをコード埋込型に変更しました。
WEBマーケティングの守備範囲
デジタルマーケティングが注目されているとはいえ、「これまでのWEBマーケティングの呼び名が変わっただけでは?」と感じる方もいると思います。そこでまずは、WEBマーケティングと呼ばれてきたマーケティング活動の内容を振り返ってみます。
国内で「WEBマーケティング」と呼ばれてきた内容
- ホームページ一つ(あるいは複数)を対象とする
- ホームページへのアクセスを増やす(SEO/WEB広告)
- KGIはホームページからの問い合わせ
- ホームページ内のユーザの行動を計測し、コンテンツ改善
まさに今自社のWEBマーケティング活動として上記の内容に取り組んでいる方も多いと思います。しかし、スマホやタブレットといった携帯端末が普及したことにより、ユーザはSNSをはじめとしたアプリや、メールやLINEといった通信手段を行き来するようになり、上記のような内容だけではユーザへの効果的なアプローチが難しくなりました。
デジタルマーケティングの守備範囲
上で触れたように、これまでのWEBマーケティングでは効果的なマーケティング活動が困難になった今、注目されているのが「デジタルマーケティング」なのです。
では次に、デジタルマーケティングの守備範囲についてみていきます。
「デジタルマーケティング」で行う内容
- 目的の異なる複数サイトをグループで捉える(例:コーポレート/オウンドメディア)
- メールマーケティング(ステップメールなど)
- ソーシャルメディアマーケティング
- アプリマーケティング(スマホアプリなど)
- デジタルクーポンなどの端末付与サービス(電子決済など)
- 上記複数チャネルにまたがるリードの動向把握
対象が広すぎて全てを紹介することはできませんが、ユーザに紐づくデータを持ったものは殆どがデジタルマーケティングの対象となります。
デジタルマーケティングはWEBマーケティングを含む
繰り返しになりますが、デジタルマーケティングはユーザに紐づくデータを持ったものを対象とする俯瞰的なマーケティング活動です。
WEBマーケティングとの関係性は簡単に示すと以下のようになります。
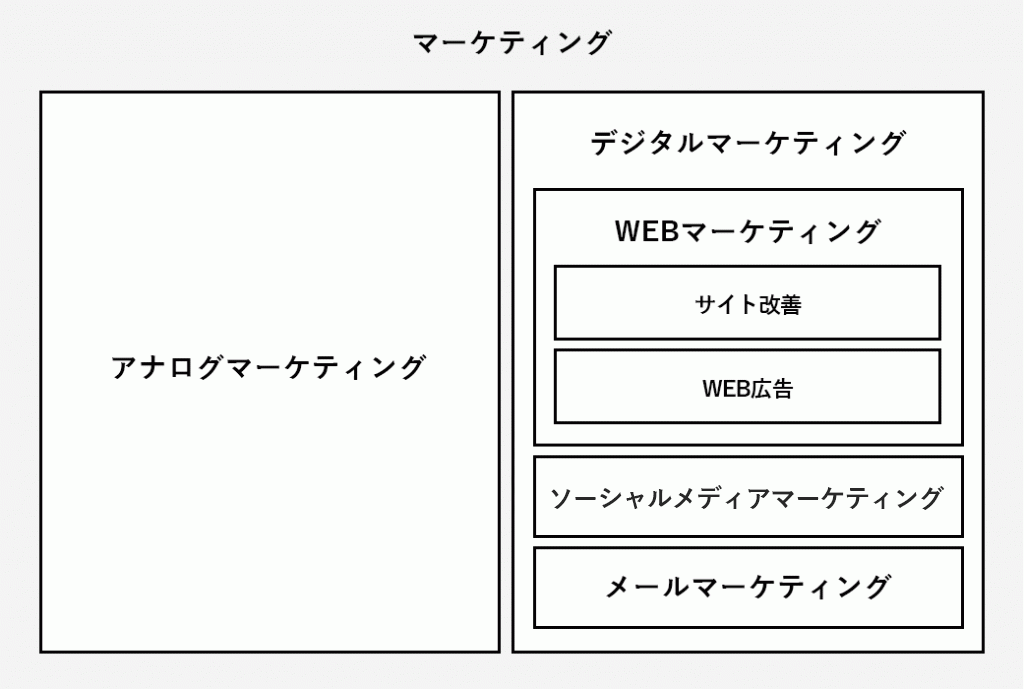
最も広義な活動として「マーケティング」があり、その中のデジタル分野を扱うものが「デジタルマーケティング」です。そしてその中に、これまで個別に取り組まれてきた「WEBマーケティング」「ソーシャルメディアマーケティング」「メールマーケティング」などが含まれる構図です。
同じように、今度はマーケット(市場)とデジタルマーケティングの相関図を見てみましょう。
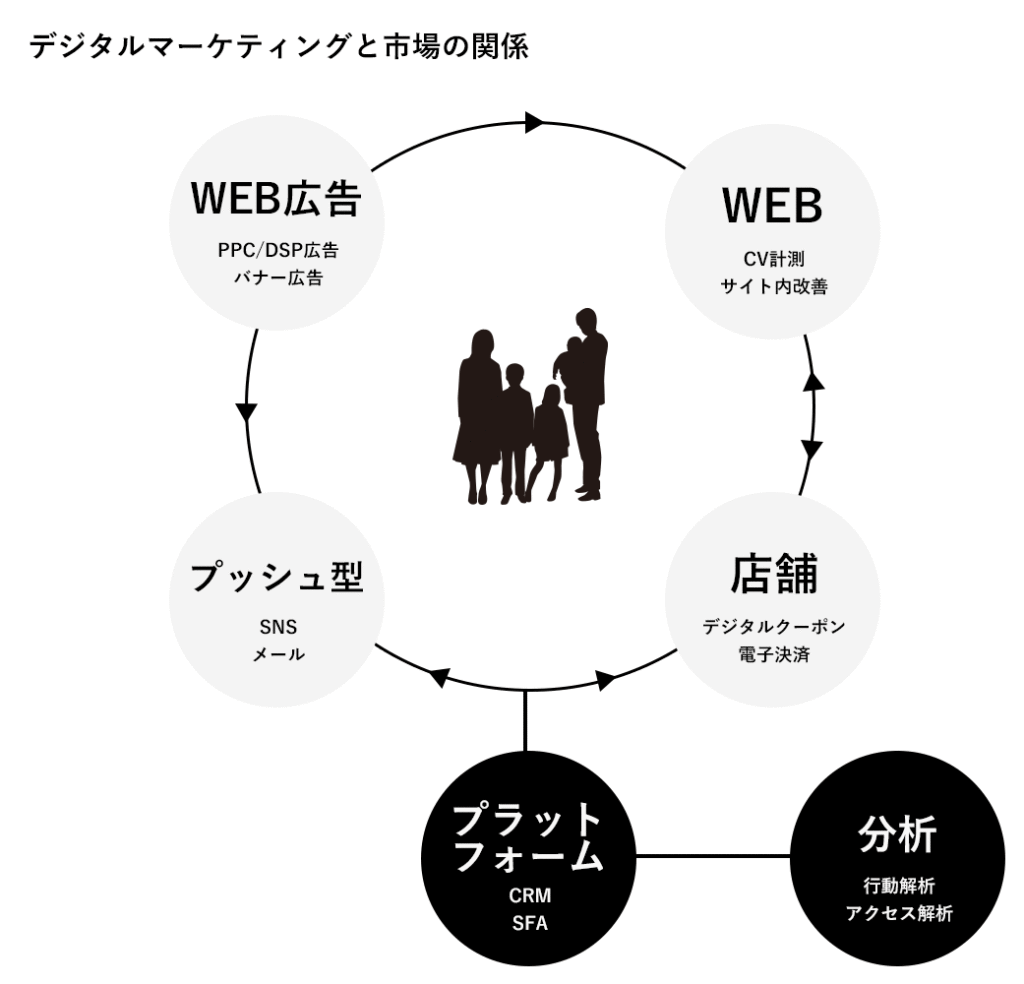
完全デジタルから、(アナログでの動向を含めますが)店舗での電子決済まで、WEBマーケティング単体よりもより多角的にユーザと接触できることが分かると思います。
なお、デジタルマーケティングとマーケット(市場)との関係性については株式会社オージス総研が詳しくまとめてくれているので、ぜひご覧ください。
国内デジタルマーケティング市場
実際に国内でデジタルマーケティングが行われているのかを説明するために、
今度は矢野経済研究所が行った「国内のデジタルマーケティングサービスの市場規模(事業者売上高ベース)に関する調査結果」を見てみます。
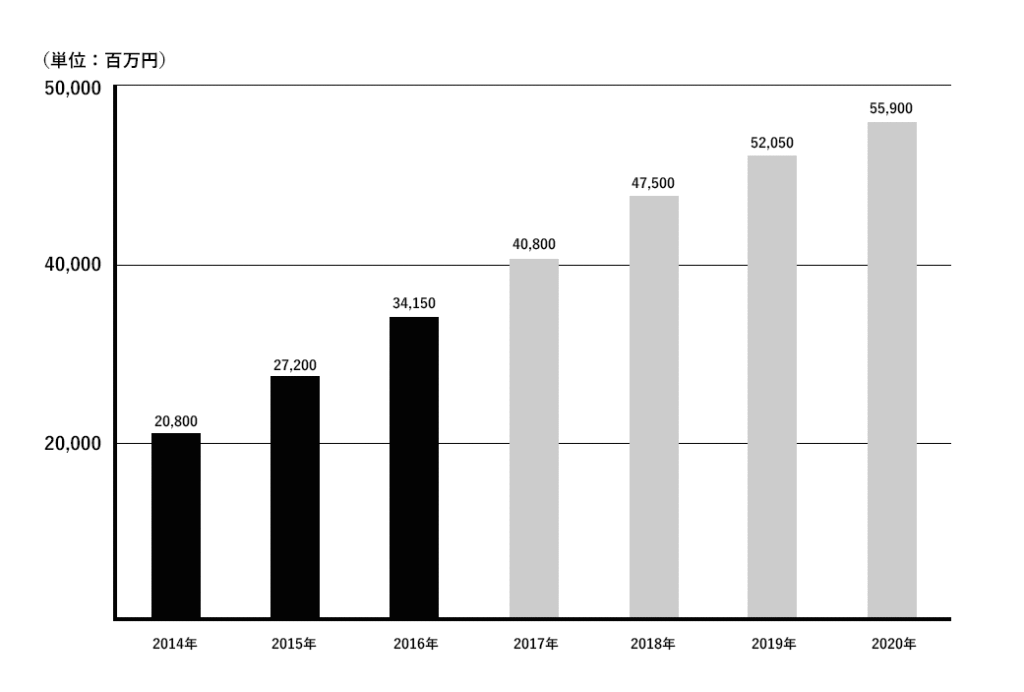
2014年から2016年まで右肩上がりで増えており、2020年にはなんと559億円もの市場規模になると予測されています。
デジタルマーケティングに関する国内企業へのアンケート結果
もうひとつのデータ、日経BPコンサルティングが2015年に700人のマーケティング活動関与者へ行ったアンケートを見てみましょう。
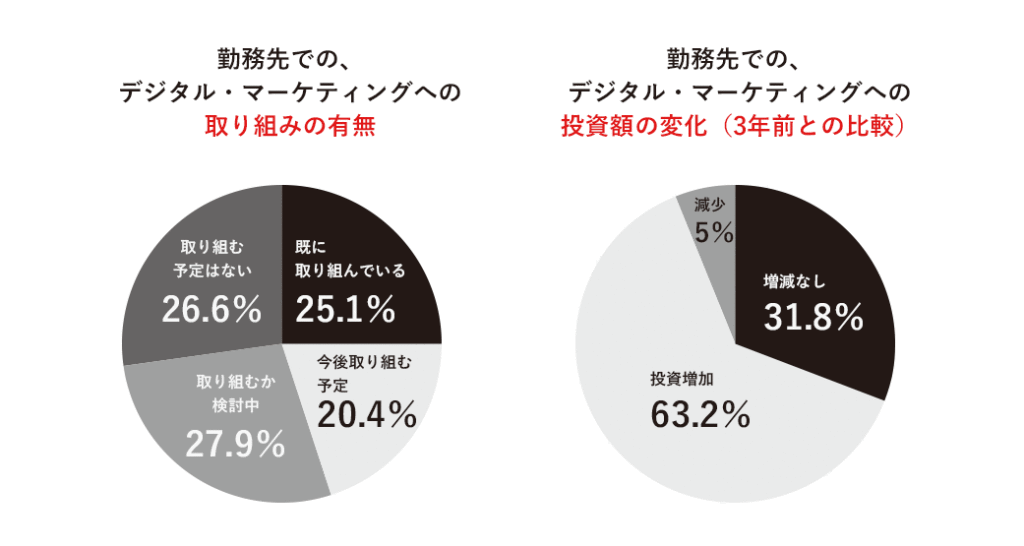
上のグラフではデジタルマーケティングへの取り組み状況、同分野への投資傾向から、実際にデジタルマーケティングに取り組む企業が増えていることが見えてきます。
また、大手広告代理店の電通も2016年7月に、デジタルマーケティング分野専門の子会社として電通デジタルを設立しています。
デジタルマーケティング導入後に見える課題
ここまでデジタルマーケティングの長所について触れてきましたが、まだ未成熟な市場ゆえに、導入後の企業が抱える課題もあります。
クロージング率の計測が難しい
デジタルマーケティングは、複数チャネルを移動するユーザの動向を俯瞰的に計測することで、より見込みの高いユーザ(リード)を見つけることができます。
しかし業務の現場では「実際に導き出したリードを、営業担当がクロージングできたのか計測できていない」など、有効に活用できているのか不安を感じる企業もあるようです。
こういった部分についてはSFAツールなどと組み合わせて活用していくことで計測可能になるため、必要に応じて外部コンサルティングを依頼すると効果的です。
適切なKPI、KGIの設定が難しい
こちらはマーケティング活動に不慣れな企業でよく聞かれる課題です。
KPI、KGIはマーケティングだけでなくホームページ制作などでも重要となる考え方ですが、「WEBマーケティング」を行ってきた方でも意外と意識してこなかった方が多いのが現状です。
どんな目的でデジタルマーケティングを行うのかによって施策は様々なので、デジタルマーケティング導入に合わせて、社内にノウハウを構築していきましょう。
海外ではデジタルマーケティングはもはや当たりまえ
マーケティングの最先端アメリカをはじめとする海外では、デジタルマーケティングは当たり前の施策となっています。
そこで最後に、海外で主流のデジタルマーケティングをいくつかご紹介します。
チャットアプリ
エフェメラルマーケティング (Ephemeral Marketing)とも呼ばれる手法で、和訳すると「つかの間のマーケティング」という意味です。
ホームページへアクセスした時などに、リアルタイムにオペレーターとチャットができ、質問できるような機能で、メールや電話よりも気軽にコンタクトがとれるため、海外では多くの企業が導入しています。
最近では日本でもチャットプラスといったツールが提供されていたり、同じような機能を持ったホームページに出会ったことがある方もいるのではないでしょうか。
マーケティングオートメーション
マーケティングオートメーションはデジタルマーケティングの代名詞ともいえるツールです。ホームページだけでなくメールやSNSなどの複数チャンネルを行き来するユーザの行動を一つの流れとして計測することができ、その行動パターンに応じて自動で施策を実行・変更できるため、リードナーチャリングに最適な手法と考えられています。
マーケティングオートメーションについては「マーケティングオートメーションとは」をご覧ください。
まとめ
ここまでにデジタルマーケティングの特徴や課題、WEBマーケティングとの違いについて触れてきました。
デジタルマーケティングに取り組むかを検討していた方や、今日初めてデジタルマーケティングを知った方にとって、この記事が導入のひとつのきっかけになれればと思います。

 WEB担当者のためのスキルアップノート
WEB担当者のためのスキルアップノート